|
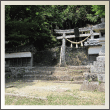 |
延暦年間(782〜805)信濃国の諏訪大明神の分霊を勧請し、赤石の地に奉斎った神社です。
 豊川市長沢町日焼53 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市長沢町日焼53 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
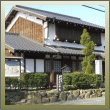 |
江戸時代をイメージした昔風の建物です。
内外にベンチを配し旅行者が足をのばしてくつろげる空間になっています。
 豊川市赤坂町紅里140-1 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市赤坂町紅里140-1 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
 |
大聖寺の境内、西北の隅に石柵に囲まれて建っているのが、今川義元の胴塚です。
 豊川市牛久保町岸組66 TEL:0533-72-3246 豊川市牛久保町岸組66 TEL:0533-72-3246
|
|
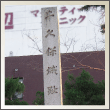 |
牛久保城は三河国宝飯郡牛久保にあった平城です。
享禄2年(1529年)に宝飯郡の牧野城主であった牧野成時(古白)の子、成勝が築城したと伝えられています。
 豊川市牛久保町城跡 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市牛久保町城跡 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
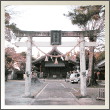 |
奈良時代の天平神護年間(765)に三河国が飢饉に見舞われた時、朝廷は倉庫を開いて救済につとめ、国司は住民に神を祀らさせるため大雀命を勧請しました。
 豊川市牛久保町常盤164 TEL:0533-89-2206(豊川市観光案内所) 豊川市牛久保町常盤164 TEL:0533-89-2206(豊川市観光案内所)
|
|
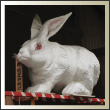 |
7世紀後半頃に建てられたといわれる 足神社は、弁慶の書と伝えられている「大般若経」585巻は国の重要文化財に,梵鐘(ぼんしょう)は県の有形文化財に指定されています。 足神社は、弁慶の書と伝えられている「大般若経」585巻は国の重要文化財に,梵鐘(ぼんしょう)は県の有形文化財に指定されています。
 豊川市小坂井町宮脇2 TEL:0533-72-3246 豊川市小坂井町宮脇2 TEL:0533-72-3246
|
|
 |
天元・永観(978〜985)の頃、時の国司 大江定基卿が三河守としての在任に際して、三河国の安泰を祈念して、出雲国大社より大国主命を勧請し、合わせて三河国中の諸社の神々をも祀られたとあります。
 豊川市国府町流霞5 TEL::0533-88-9622 豊川市国府町流霞5 TEL::0533-88-9622
|
|
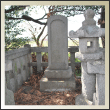 |
伊奈城は1440年頃、初代城主本多彦八郎定忠の築城に始まり、約150年間本多氏の居城でした。お松見は、後期城主の墓所になります。
 豊川市伊奈町鶴田 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市伊奈町鶴田 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
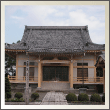 |
東三河の統一を目指す松平元康によって築かれました。現在の龍徳院の境内全部がこの砦の跡となっており、堀の内部の面積は約35アールあります。
 豊川市小坂井町樫王48 TEL:0533-72-2416 豊川市小坂井町樫王48 TEL:0533-72-2416
|
|
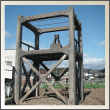 |
装荷ケーブルを渡すために、装荷線輪用櫓と木柱が造られました。
 豊川市野口町開津11 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市野口町開津11 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
 |
延徳3年(1491)に義三という僧によって開かれたといわれております。樹齢600年以上と推定される大きなクスノキが有名です。
 豊川市麻生田町松原26 TEL:0533-86-3356 豊川市麻生田町松原26 TEL:0533-86-3356
|
|
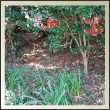 |
弥生最末期のもので、広大な地域にわたり、住居跡もいくつか発見されており、広い範囲の村があったと推測されています。ここから出土した土器にちなんでつけられた「欠山式」という形式名は、この時期の愛知県の土器を代表するものとなっています。
 豊川市小坂井町欠山 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市小坂井町欠山 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
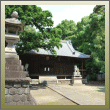 |
木造狛犬は、 県文化財に指定されており、熊野神社にあるナギの巨木は、国の天然記念物に指定されています。
 豊川市下長山町西道貝津87 豊川市下長山町西道貝津87
|
|
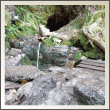 |
聖徳太子が宮路越えのとき、清水を所望された。近くの岩間に枡のような井戸があり 水が湧き出ていた。
太子はその清く冷たい水に感動し小渡井枡井戸と名付けたという。
 豊川市長沢町音羽 豊川市長沢町音羽
|
|
 |
京都伏見稲荷大社より、五神を勧請して五社稲荷社は、五穀豊穣、商売繁盛、福徳円満の神として崇敬され、毎月1日、15日の月次祭(つきなみさい)には、多くの参拝者があり、露店も出てにぎわっています。
 豊川市小坂井町欠山2 TEL:0533-72-3062 豊川市小坂井町欠山2 TEL:0533-72-3062
|
|
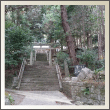 |
御油神社は昔、若一王子社とたたえられていました。その後、踊山神社となり、明治13年村社に列し、明治31年12月27日に御油神社に復称しました。
 豊川市御油町字膳之棚31番地 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市御油町字膳之棚31番地 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
 |
東海道と姫街道の分岐点で、昔から佇む常夜灯が今も残ります。
 豊川市御油町行力1-31 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市御油町行力1-31 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
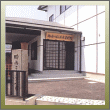 |
国の天然記念物に指定されている御油の松並木と御油宿に関する資料が展示されています。
 豊川市御油町美世賜183 TEL:0533-88-5120 豊川市御油町美世賜183 TEL:0533-88-5120
|
|
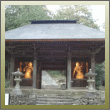 |
財賀寺は聖武天皇の勅願により、僧・行基によって開創された寺で、本尊は千手観音です。
 豊川市財賀町観音山3 TEL:0533-87-3494 豊川市財賀町観音山3 TEL:0533-87-3494
|
|
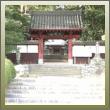 |
西明寺には多くの宝物が保存されている他、日本医学の恩人・ベルツ博士の供養塔があります。
 豊川市八幡町寺前7 TEL:0533-87-2251 豊川市八幡町寺前7 TEL:0533-87-2251
|
|
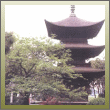 |
文武天皇の詔を受けて建立された寺で、弁財天が本堂内の宮殿にまつられています。
 豊川市豊川町波通37 TEL:0533-86-9661 豊川市豊川町波通37 TEL:0533-86-9661
|
|
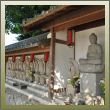 |
境内には広重の東海道五十三次に描かれ、大橋屋から移植されたとされるソテツがあります。
 豊川市赤坂町西裏88 TEL:0533-87-3862 豊川市赤坂町西裏88 TEL:0533-87-3862
|
|
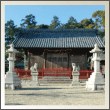 |
境内社に護国神社・秋葉神社があり、入り口と境内左側に、ご神木があります。裏側には木々が茂っています。
 豊川市金屋本町1-61 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市金屋本町1-61 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
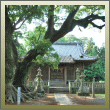 |
境内の2本のクスノキは、推定樹齢千年を数え夫婦クスノキとして親しまれています。
 豊川市赤坂町 豊川市赤坂町
|
|
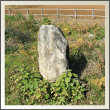 |
本宮山の南麓に広がる炭焼平から柿木平にある古墳群になります。1952年に農林省の事業で開墾が進められた際に発見されました。
 豊川市東上町炭焼平154 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市東上町炭焼平154 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
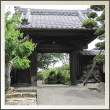 |
蓮如上人より寺号を誓林寺、山号を乙葉山を賜りました。その後、領主松平氏により古谷山と改められました。本堂は建て替えられ、現在は、文政七年(1824年・棟木より)建立されたものです。
 豊川市長沢町下市3 TEL:0533-87-3305 豊川市長沢町下市3 TEL:0533-87-3305
|
|
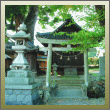 |
境内に推定樹齢800年のクスノキの巨木がそびえています。
 豊川市赤坂町関川111番地 TEL:0533-89-2206(豊川観光協会) 豊川市赤坂町関川111番地 TEL:0533-89-2206(豊川観光協会)
|
|
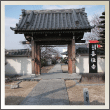 |
山門を入りまっすぐのところに庚申様の祠があり、いぼ神様の庚申碑の祠の右にある大きなお堂が御本堂になります。
 豊川市小坂井町北浦11 TEL:0533-89-2206(豊川観光協会) 豊川市小坂井町北浦11 TEL:0533-89-2206(豊川観光協会)
|
|
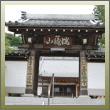 |
本殿(大雄殿)御本尊には釈迦三尊佛、内陣壁面には雲中供養菩薩を祀っています。
 豊川市萩町倉戸81番地 TEL:0533-88-2325 豊川市萩町倉戸81番地 TEL:0533-88-2325
|
|
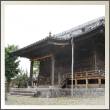 |
旧蔵子村82戸の産土神です。神体に赤坂の御嶽城より十一面観音像を勧請し、牛頭天王として奉祀しましたが、その後元和6年(1620)山城国祇園社より改めて牛頭天王を勧請しました。
 豊川市蔵子1丁目25-18 TEL:0533-89-2206(豊川観光協会) 豊川市蔵子1丁目25-18 TEL:0533-89-2206(豊川観光協会)
|
|
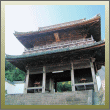 |
牛久保城主・牧野氏の菩提寺で、その山門は県指定文化財となっています。徳川家ともゆかり深い名刹です。
 豊川市御津町広石御津山5 TEL:0533-75-2325 豊川市御津町広石御津山5 TEL:0533-75-2325
|
|
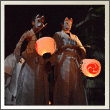 |
稲荷社として、大永年間(1511年〜)には、すでに信仰を受けている由緒ある神社で、豊川市では豊川稲荷、五社稲荷社に次ぐ稲荷の古刹です。
 豊川市為当町宮脇32番地 TEL:0533-75-3303(宮司宅)[動画] 豊川市為当町宮脇32番地 TEL:0533-75-3303(宮司宅)[動画]
|
|
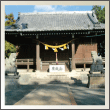 |
天正3年(1575)5月、長條の合戦の兵火により社殿、古文書を失居ましたが、慶長16年(1611)の棟札に奉新造立金山大権現とあります。
 豊川市中条町宮坪22番地 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市中条町宮坪22番地 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
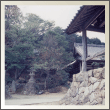 |
三河の国司大江定基との別れを悲しんで自害した赤坂の長者の娘力寿姫の菩提を弔うために建てられたました。山中には姫の墓もあります。
 豊川市赤坂町西裏99 TEL:0533-87-2812 豊川市赤坂町西裏99 TEL:0533-87-2812
|
|
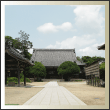 |
昔、前芝村(現豊橋市)に東漸寺という真言宗の寺が廃寺となり延命地蔵尊を祀る小堂だけになりました。ところが、津波によりこの地蔵尊が、伊奈の地に流れ着いたので、村人はこれを崇めて祀っていました。
 豊川市伊奈町縫殿58 TEL:0533-72-2756 豊川市伊奈町縫殿58 TEL:0533-72-2756
|
|
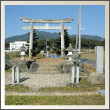 |
東上御番所は分一番所と呼ばれ、江戸幕府の財源とするため、川を下る船の積み荷に対する分一税を徴収していました。
 豊川市東上町宮沢 TEL:0533-89-2206(豊川観光協会) 豊川市東上町宮沢 TEL:0533-89-2206(豊川観光協会)
|
|
 |
永享年間(1429〜1441)龍月日蔵和尚によって創建され、寺号を洞言庵としました。80年後の永正年間(1504〜1521)に堂宇を建立し、伽藍を整え、名を白蓮院招賢山東林寺と改めました。
 豊川市御油町今斉28 TEL:0533-89-2206(豊川観光協会) 豊川市御油町今斉28 TEL:0533-89-2206(豊川観光協会)
|
|
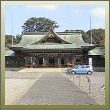 |
厄難消除等東海地方各面から多くの参拝客が訪れます。
田遊祭(里宮) 粥占祭(奥宮)
 豊川市一宮町西垣内2 TEL:0533-93−2001(代)[動画] 豊川市一宮町西垣内2 TEL:0533-93−2001(代)[動画]
|
|
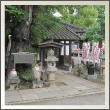 |
大きなケヤキが数本茂った一隅に小さなお堂が建てられ、その中に深さ1mほどの井戸があります。
 豊川市豊川西町151 TEL:0533-84-7453 豊川市豊川西町151 TEL:0533-84-7453
|
|
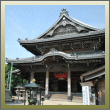 |
商売繁盛の神様として全国的に知られる豊川稲荷。
 豊川市豊川町1 TEL:0533-85-2030(代) 豊川市豊川町1 TEL:0533-85-2030(代)
|
|
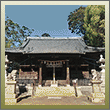 |
当神社には、本社(豊川西町134)と元宮(豊川町仁保通)の二つの社があります。本社の御祭神は進雄命(すさのおのみこと)です。
 豊川市豊川西町134 TEL:0533-86-2920 豊川市豊川西町134 TEL:0533-86-2920
|
|
 |
本殿は、文明9年(1477)に建立されたもので、明治40年に国の重要文化財に指定されています。
 豊川市八幡町本郷16 TEL:0533-88-3723 豊川市八幡町本郷16 TEL:0533-88-3723
|
|
 |
旅籠大橋屋建物(豊川市指定文化財)が所有者の方より豊川市にご寄附いただきました。今後、旅籠大橋屋の一般公開に向け、耐震補強も含めた保存整備の設計作業や工事を行う計画です。
 豊川市赤坂町紅里127番地 豊川市赤坂町紅里127番地
|
|
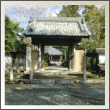 |
今からおよそ千年前、三河国司大江定基公の室「花井媛」が、霊泉が涌き出て四季の花咲く此の地に「地藏尊」を奉じて菴を結ばれことに始まります。
 豊川市花井町13-10 TEL:0533-86-2079 豊川市花井町13-10 TEL:0533-86-2079
|
|
 |
全国でも屈指の縄文人骨出土遺跡として知られ、現在までに約90体もの人骨が確認されています。
 豊川市平井町 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市平井町 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
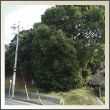 |
この古墳は東三河最大級の前方後円墳で,全長94m,前方部幅約65m,後円部直径56m,高さ6.5m,後円部を東に向けたものです。
築造の時期は,古墳時代の中期と考えられます。
 豊川市八幡町上宿 TEL:0533-85-3775(豊川市地域文化広場ふるさと資料館) 豊川市八幡町上宿 TEL:0533-85-3775(豊川市地域文化広場ふるさと資料館)
|
|
 |
豊川海軍工廠の爆撃でなくなった人々の霊を慰めるため、昭和40年に建てられました。
 豊川市諏訪1丁目 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市諏訪1丁目 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
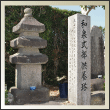 |
大同2年(807)に創立されたお寺です。堂内にある絵馬は、馬が絵から抜け出し畑の麦を食べて困ったとの伝説があり、絵から抜け出ないように馬の足に灸をすえた跡が残っています。
 豊川市小坂井町平口76 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市小坂井町平口76 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
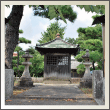 |
千歳通のおしゃれな街並みの中に残る、小さな廟。これは、第2代牛久保城主・牧野成定の墓所です。
 豊川市千歳通4丁目 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市千歳通4丁目 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
 |
三河国分寺跡は、大正11(1922)年に国史跡の指定を受けた、学術的な価値の高い遺跡です。塔跡には礎石が2つ現存しており、往時をしのぶことができます。
 豊川市八幡町本郷31 豊川市八幡町本郷31
|
|
 |
三河国分寺跡の中に「国分寺」があります。国分寺は、天平13年(741)に聖武天王が発した「国分寺建立の詔」により、東大寺を総本山として諸国に建てられました。
 豊川市八幡町本郷31 豊川市八幡町本郷31
|
|
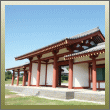 |
寺域は約150メートル四方で、現在発見されている国分尼寺の中では最大のものです。
 豊川市八幡町忍地127-1 TEL:0533-88-5881 [動画] 豊川市八幡町忍地127-1 TEL:0533-88-5881 [動画]
|
|
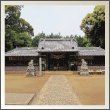 |
穂の国(今の東三河)が西三河(当時の三河国)と一国になり、三河国となりその三河国庁がこの総社の東側に置かれておりました。
 豊川市白鳥町上郷中1 豊川市白鳥町上郷中1
|
|
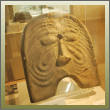 |
三河国分尼寺跡公園の正面にある資料館です。
資料館内では、展示や映像によって古代三河国の概要を解説しているほか、最新の発掘調査情報を発信しています。
 豊川市八幡町忍地127-1 TEL:0533-88-5881 豊川市八幡町忍地127-1 TEL:0533-88-5881
|
|
 |
1570年に龍玄法印不動尊は、人皇第106代正親町天皇の元亀元年(1570年)当山第1世龍玄法印によって開山された、みちびき不動と病封じの寺として知られています。
 豊川市麻生田町縄手69-1 TEL:0533-86-2570 豊川市麻生田町縄手69-1 TEL:0533-86-2570
|
|
 |
御津神社の祭神は大国主命で、紀元前に建てられたといわれています。
 豊川市御津町広石祓田70 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市御津町広石祓田70 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
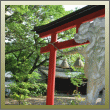 |
宇治川の先陣争いを描いた絵馬があり市の指定文化財に指定されています。
 豊川市赤坂町宮路1120番地 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市赤坂町宮路1120番地 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
 |
妙劉寺は慶長5年(1600)の創建ですが、「陽広山東郷寺」から「迦葉山妙劉寺」に名前を変更し、現在の場所へ移りました。
 豊川市東上町滝ノ入8 TEL:0533-93-2700 豊川市東上町滝ノ入8 TEL:0533-93-2700
|
|
 |
 |
|
薬師堂
|
|
豊川稲荷の門前町にあり、“お薬師さん” という愛称で親しまれています。薬師堂は、豊川 稲荷のお堂の一つで平成27年に建て替えられました。
毎月末に開かれる「いなり楽市」の会場にもなっています。
 豊川市門前町7 豊川市門前町7
|
|
 |
大和保育園の裏手にある大イチョウは、高さは約25mで、枝は水平方向に10m以上あります。
 豊川市豊津町割田53-1 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市豊津町割田53-1 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
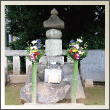 |
牛久保町寺町は、その名からうかがえるように多くの寺が建てられている所です。その中の一つ、長谷寺(ちょうこくじ)には、風林火山で知られる山本勘助の墓があります。
 豊川市牛久保町八幡口97 TEL:(0533)85-3224 豊川市牛久保町八幡口97 TEL:(0533)85-3224
|
|
 |
元豊川市白鳥の白鳥神社に鎮座して白鳥三御子明神と称して、「三河国内神名帳」に従四位上の明神とあります。
 豊川市桜町2丁目7番地8 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市桜町2丁目7番地8 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
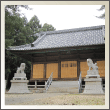 |
若宮八幡大神(大雀命)と誉田別命(石清水)と伊奈那美命(熊野)をお祀りしております。
 豊川市伊奈町宮坪1 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会) 豊川市伊奈町宮坪1 TEL:0533-89-2206(豊川市観光協会)
|
|
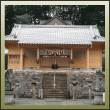 |
安産の神社としての信仰が強く、拝殿には多くの前掛けを奉納しています。
 豊川市東上町権現1-1 TEL:(0533)93-0139 ※10:00〜14:00まで 豊川市東上町権現1-1 TEL:(0533)93-0139 ※10:00〜14:00まで
|
|